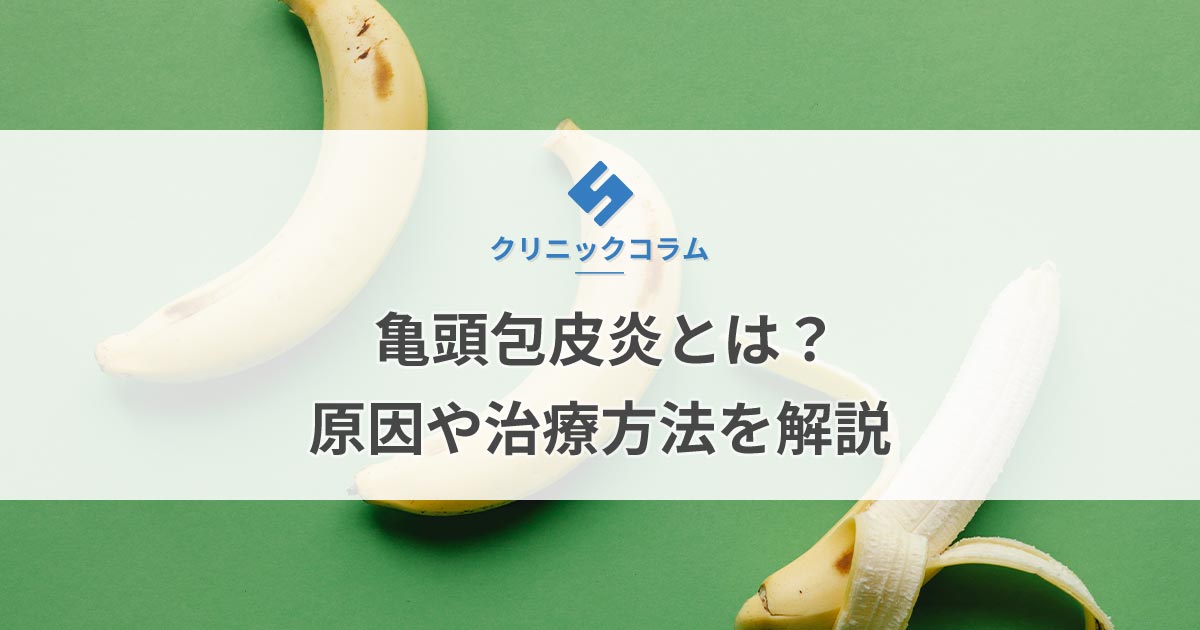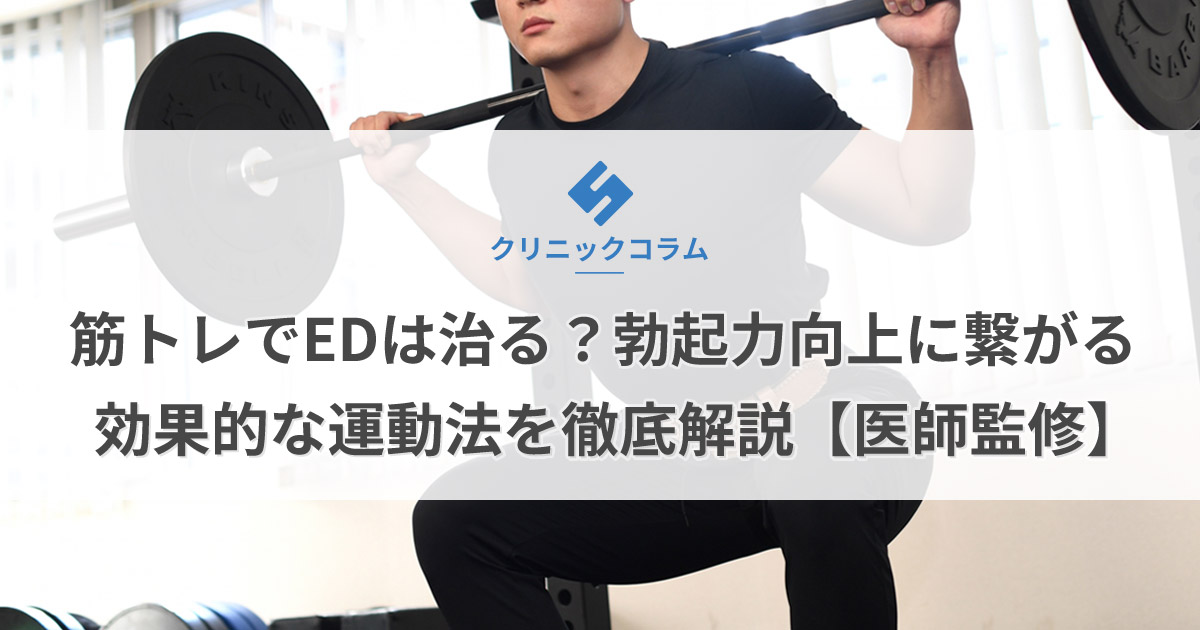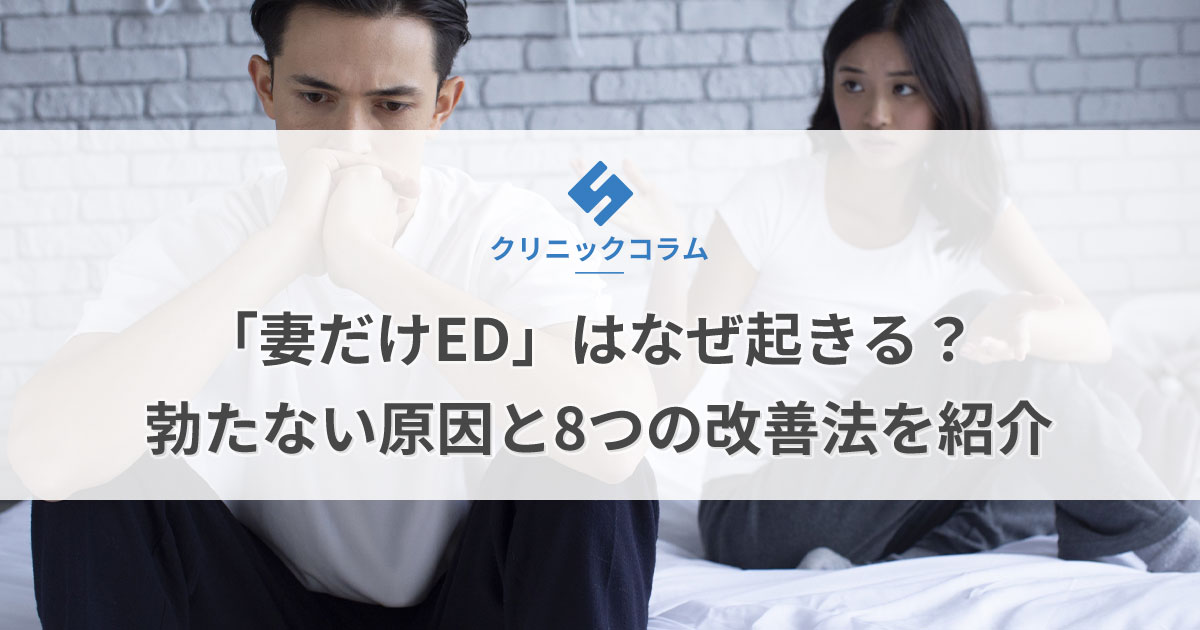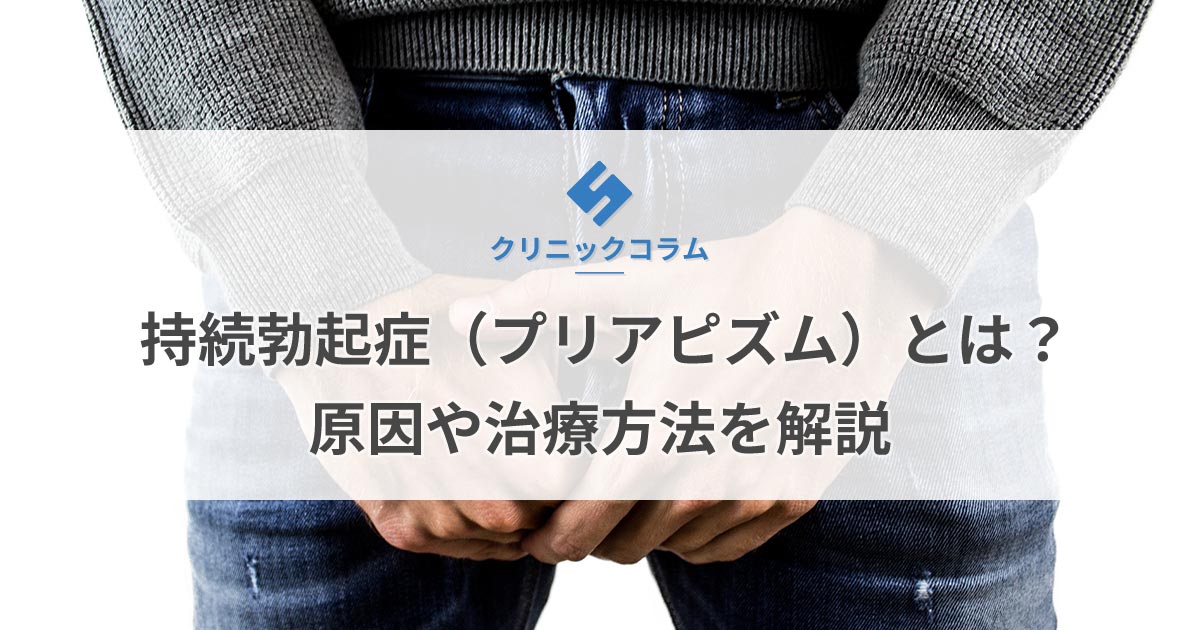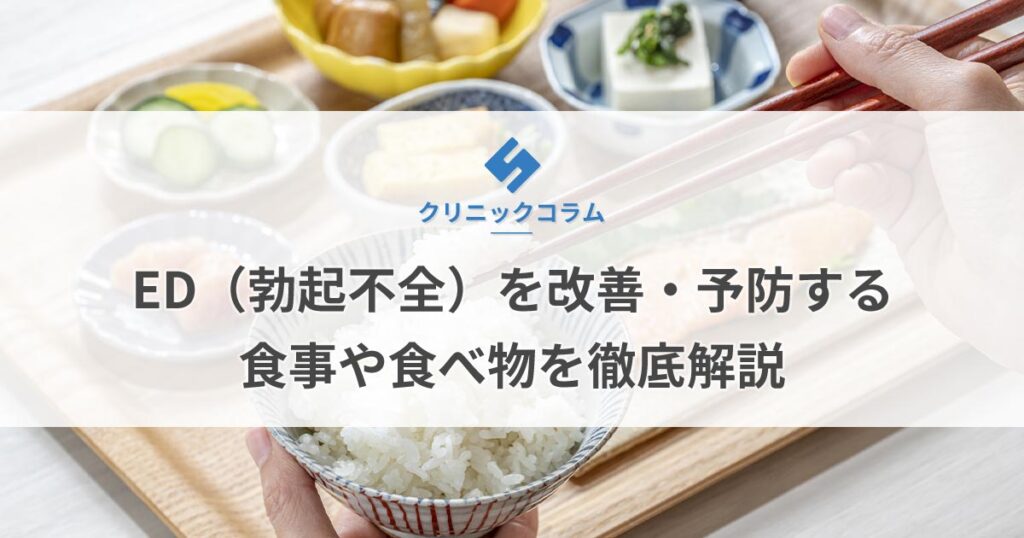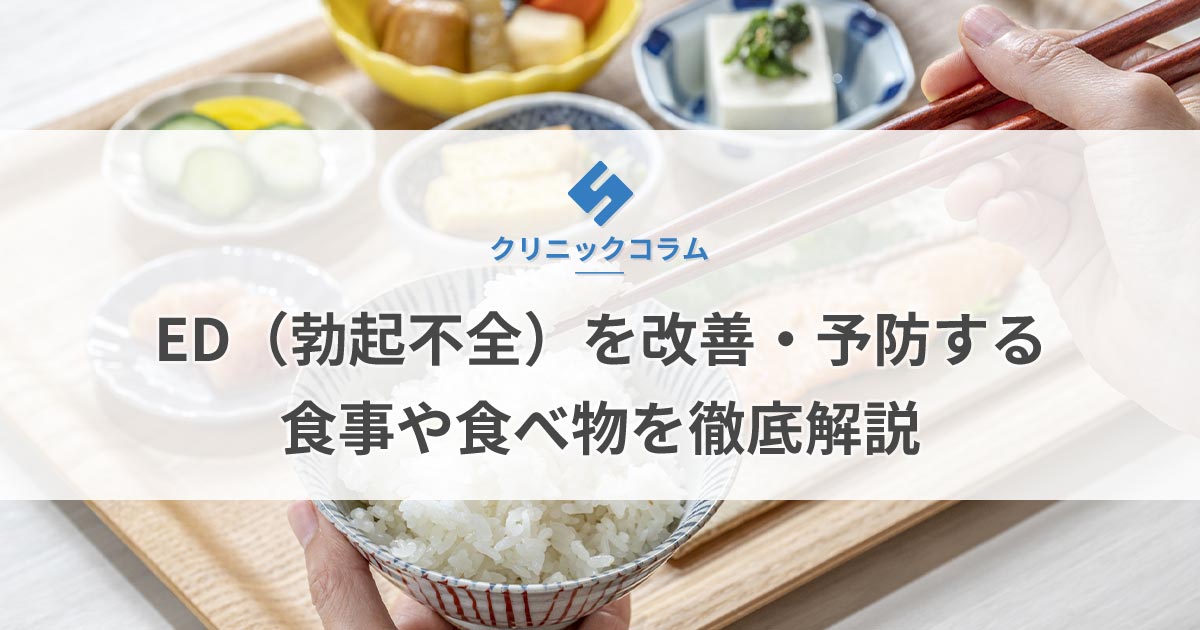
ED(勃起不全)は、ED治療薬の服用や外科治療(ICI治療など)で改善が見られる場合がほとんどです。
しかし、ED治療薬は効果の持続時間に限界があります。
ICI治療などの外科治療も、一時的な勃起促進効果しかありません。
EDを改善するには、ED治療薬や外科治療とともに生活習慣を改善する必要があります。
生活習慣を改善する方法の一つが「食事」です。
今回は、EDの改善・予防が期待できる食べ物、飲み物について解説します。
くわえて、EDを悪化させる可能性のある食べ物、飲み物も紹介していきます。
※リンクをクリック、またはタップすると、ページ内の項目へ移動します
ED(勃起不全)でお悩みのあなたへ
ED治療は、新橋ファーストクリニックにお任せください。
バイアグラ、レビトラ、シアリスなどのED治療薬を取り扱っています。
当クリニックの特長
- 国内正規品のED治療薬を処方
- 来院時の診察料、処方料などは全て無料
- 新橋駅から徒歩3分の好アクセス
- 予約なしで当日に来院してもOK
\ ED治療薬は260円~1,580円 /※
※ 表示の最低価格は初診患者様に処方するED治療薬です
※ 初診と再診で価格が異なるED治療薬があります
EDと食事は関係している

EDの一種である「器質性ED」は、食生活と関係があると言われています。
器質性EDとは、身体的な原因から勃起ができない、または勃起が不十分になることです。
糖尿病、高血圧、肥満などの生活習慣病は動脈硬化のリスクがあります。
動脈硬化は血管や神経を損傷し、EDの発症に繋がることがあります。
乱れた生活習慣を改善する方法の一つが食事です。
食生活(生活習慣)を改善することで、血流の改善が見込めます。
血流が良くなって陰茎に血液が流れ込むことで、勃起の維持が期待できます。
ただし、EDを完全に改善できる食べ物や飲み物は存在しません。
食事はあくまでEDの予防や悪化を防ぐものとお考えください。


EDを予防・改善してくれる食べ物や飲み物
前述のとおり、EDを根本的に改善できる食べ物や飲み物はありません。
しかし、EDが起きるメカニズムからすると、EDの予防や改善が期待できる食べ物や飲み物が存在するのも事実です。
EDの予防や改善が期待できる食べ物や飲み物は、主に「血流を改善してくれる食材」と「精力や性機能が高まる食材」の2つに分けられます。
それぞれ、具体的な食材がどのようにEDの予防や改善に効果的なのかご説明します。
また、食生活の乱れはEDだけでなく、様々な病気を誘発します。
食生活において、EDを予防や改善するということは、ED以外の病気も予防することに繋がるので、是非参考にしてください。
血流を改善してくれる食材
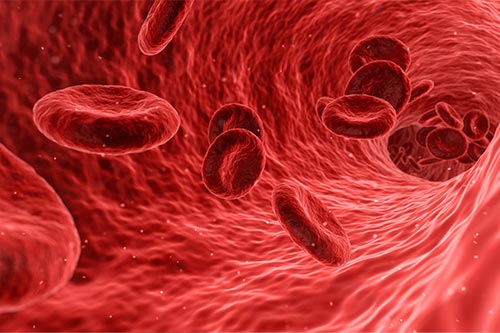
勃起を促すには、血管内の血液の潤滑な流れが欠かせません。
また、血管の拡張性や柔軟性も重要になります。
血管が硬く、血管の拡張が起こりにくいとスムーズな血流が抑えられてしまい、EDの原因になってしまいます。
そのため、血管の拡張性や柔軟性を高めたり、血液をサラサラにして血流を良くしたりする食材はEDの予防や改善に役立つと考えられます。
血液をサラサラにする食事は、「おさかなすきやね」食が有名です。
「おさかなすきやね」とは、内臓脂肪研究の第一人者である医師の栗原 毅(くりはら たけし)氏によって提唱された、血液の流れを良くする効果が期待できる食材の頭文字を合わせた言葉です。
- お ⇨ お茶(緑茶や烏龍茶、ほうじ茶など)
- さ ⇨ 魚(サバ、イワシ、サンマなどの青魚)
- か ⇨ 海藻類(わかめ、昆布など)
- な ⇨ 納豆
- す ⇨ 酢(酢酸、クエン酸)
- き ⇨ キノコ類(シイタケ、キクラゲ、マイタケなど)
- や ⇨ 野菜類(ニンジン、カボチャ、ピーマンなど)
- ね ⇨ ネギ類(長ネギ、玉ネギ、にんにくなど)
ほかにも血液の流れの改善に役立つ食材があるので、「おさかなすきやね」の食材とともに詳しくご紹介します。
主に血流を改善してくれる食材
- お茶(緑茶、烏龍茶、ほうじ茶など)
- 青魚(サバ、イワシ、サンマなど)
- 海藻類(わかめ、昆布など)
- 納豆
- お酢(酢酸、クエン酸)
- キノコ類(シイタケ、キクラゲ、マイタケなど)
- 野菜類(ニンジン、カボチャ、スイカなど)
- ネギ類(長ネギ、玉ネギ、にんにくなど)
- 果物類(柑橘類、イチゴ、ブドウなど)
- カカオ豆(ココア、高カカオチョコレートなど)
※リンクをクリック、またはタップすると、ページ内の項目へ移動します
お茶(緑茶、烏龍茶、ほうじ茶など)

緑茶や烏龍茶、ほうじ茶などに含まれる渋みの成分の「カテキン」には、抗酸化作用があります。
活性酸素の生成を抑制し、血管の老化を防ぐことで、血液をサラサラにしてくれる効果が期待できます。
また、いわゆる悪玉コレステロールと言われる、LDLコレステロールの吸収を抑え、排出を促す作用や糖の吸収を抑え、血糖値の上昇を抑制する作用もあります。
EDの原因に繋がる肥満やEDの原因そのものになる糖尿病を防ぐ効果も期待できます。
毎日の習慣に緑茶や烏龍茶などを取り入れてみましょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| カテキン | 抗酸化作用 LDLコレステロール低下作用 血糖値上昇抑制作用 |
青魚(サバ、イワシ、サンマなど)

血流改善には、サバやイワシ、サンマ、アジなどの背中が青い魚いわゆる青魚がおすすめです。
青魚には、生きていくうえで欠かせない重要な栄養素である不飽和脂肪酸の一種、「DHA(ドコサヘキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」という成分が多く含まれています。
DHAやEPAは血小板凝集を抑制されたり、中性脂肪の低下になったり、効果が期待されています。
血小板の凝集が抑制されることで、ドロドロした血液が溶かされサラサラになり、動脈硬化が防げるので、EDの予防や改善に期待できます。
また、肥満はEDの原因になるといわれる、糖尿病や高血圧などの生活習慣病のリスクを高めてしまいます。
血中の余分な中性脂肪の低下によって、脂肪の燃焼が促進され、肥満や脂質異常を防げるので、結果としてEDの予防に繋がることも期待できます。
DHAやEPAは、体内ではほとんど生成されない栄養素なので、サバやイワシ、サンマなどの青魚から積極的に摂取しましょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 中性脂肪低下作用 血小板凝集抑制作用 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) |
海藻類(わかめ、昆布など)

わかめや昆布などの海藻類に含まれるぬめり成分の「アルギン酸」には、血糖値の上昇を抑える効果があります。
また、アルギン酸は水溶性食物繊維なので、中世脂肪の吸収を抑え、体外へ排出する働きも持っています。
血糖値の上昇が抑えられると、血圧の上昇も抑えられるので、EDの原因となる糖尿病や高血圧、動脈硬化などを予防することができます。
その他、海藻類には、基礎代謝を促進する「ミネラル」も豊富なため、肥満予防にも繋がります。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 中性脂肪低下作用 血小板凝集抑制作用 |
| ミネラル | 基礎代謝促進作用 |
納豆

納豆に多く含まれるタンパク質分解酵素の「ナットウキナーゼ」には、血栓を溶かして血液をサラサラにする効果があります。
また、脂質の代謝を促進する「ビタミンB2」も豊富なため、肥満予防にも繋がります。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| ナットウキナーゼ | 線維素溶解作用 |
| ビタミンB2 | 脂質分解促進作用 |
お酢(酢酸、クエン酸)

お酢には、主成分の「酢酸」や有機酸の一種、すっぱい成分の「クエン酸」が豊富に含まれています。
酢酸やクエン酸には、血糖値の上昇を抑えたり、赤血球の膜を柔軟にして、血管への負担を軽減したりする効果があります。
また、乳酸の生成を抑制し、疲労を回復する効果もあります。
クエン酸を効率的に摂取するなら梅干しやレモンもおすすめです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 酢酸・クエン酸 | 血糖値上昇抑制作用 乳酸生成抑制作用 |
キノコ類(シイタケ、キクラゲ、マイタケなど)

シイタケやキクラゲ、マイタケなどのキノコ類には、「不溶性食物繊維」が豊富に含まれており、血糖値の上昇を抑制してくれます。
また、キノコ類には、「β-グルカン」という成分も含まれており、血糖値の上昇抑制やコレステロールの低下に役立ちます。
β-グルカンには、白血球の一種であるナチュラルキラー細胞(Natural killer cell:NK細胞)など働きを活性化させ、免疫力を高める効果もあるため、病気やアレルギーの予防にも効果的です。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 不溶性食物繊維 | 血糖値上昇抑制作用 |
| β-グルカン | 免疫力向上作用 |
野菜類(ニンジン、カボチャ、スイカなど)

野菜類の中でも、ニンジンやカボチャ、ピーマンなどの緑黄色野菜には、「不溶性食物繊維」や「ビタミンC」が多く含まれており、血流を良くしてくれます。
野菜は、特に不溶性食物繊維が多く含まれているので、血糖値の上昇を抑制してくれる以外に便秘の予防にも役立ちます。
抗酸化物質であるビタミンCは、活性酸素の発生や働きを抑制し、血管の老化を防ぐことで、血液をサラサラにしてくれる効果が期待できます。
また、野菜類に属するスイカも血流促進に効果があります。
スイカには、アミノ酸の一種「シトルリン」という成分が多く含まれています。
シトルリンは、体内でNO(一酸化窒素)の生成を促し、血管を拡張したり、強くしなやかにしたりする作用があるのです。
血管が拡張されれば、血流もスムーズになり、血行不良の予防に繋がります。
野菜類は、1日350g以上の摂取が望ましいと言われています。
栄養価が高い季節の旬野菜を取り入れ、血流改善を目指しましょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 不溶性食物繊維 | 血糖値上昇抑制作用 |
| ビタミンC | 抗酸化作用 |
| シトルリン | 血管拡張作用 |
ネギ類(長ネギ、玉ネギ、にんにくなど)

長ネギや玉ネギ、にんにくなどのネギ類に含まれるにおい成分の「アリシン」には、血小板の凝集を抑制し、血栓の生成を予防してくれる効果があります。
ほかにも、疲労回復や血中の脂質を低下させる効果が期待できます。
また、ネギ類の中でもにんにくは、「亜鉛」を多く含むことで知られています。
亜鉛は、別名セックスミネラルと呼ばれるほど、男性の性機能と関りが深く、特に前立腺や精巣などに高濃度に含まれている成分です。
亜鉛が不足すると性機能へ顕著に影響を与えると言われているので、積極的に摂取するようにしましょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| アリシン | 血小板凝集抑制作用 |
| 亜鉛 |
果物類(柑橘類、イチゴ、ブドウなど)

柑橘類(レモンやみかん、オレンジなど)の皮や袋、スジに多く含まれるポリフェノールの一種である「ヘスペジリン」には、抗酸化作用があります。
また、毛細血管の強化や血中中性脂肪の低下などによる血流改善作用もあることが分かっています。
果汁100%のオレンジジュースなら効率的に摂取できるのでおすすめです。
朝に飲めば血流を高め、血糖値も上がり、仕事や勉強に集中できるので、生産性をアップに繋がり、ストレスを溜めにくくなるかもしれません。
ブドウの皮になどに多く含まれるポリフェノールの一種である「レスベラトロール」もまた、抗酸化作用があります。
ブドウを摂取する場合は、100%ブドウジュースや赤ワインが効率的に摂取できるのでおすすめです。
赤ワインによる、ほろ酔い程度のアルコールの摂取なら、血管を拡張させ、血流を良くしてくれます。
ただし、アルコールの毎日の過剰な摂取は、反対に血液をドロドロにしてしまうため、赤ワインは1日にグラスで約2杯が適量です。
その他、イチゴなどの果物類全般に含まれる「ビタミンE」にも血液の流れをスムーズにしてくれる強い抗酸化作用があります。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| ヘスペジリン | 抗酸化作用 |
| レスベラトロール | |
| ビタミンE |
カカオ豆(ココア、高カカオチョコレートなど)

ココアの原料であるカカオ豆に含まれる「カカオポリフェノール」には、抗酸化作用があります。
ココア以外にも高カカオチョコレートなども効率的に摂取できるのでおすすめです。
また、ココアや高カカオチョコレートには「テオブロミン」が多く含まれており、血管拡張作用があります。
カカオ豆は、抗酸化作用と血管拡張作用によって効果的に血流を改善させてくれる食材なのです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| カカオポリフェノール | 抗酸化作用 |
| テオブロミン | 血管拡張作用 |
精力や性機能を高める食材

EDを予防するためには血流を改善する食材以外にも、精力や性機能などを高める食材の摂取も重要です。
性欲の低下が原因でEDになる可能性もあるからです。
しかし、食べると性行為をしたくなるような、俗にアフロディジアック・フード(Aphrodisiac Foods:媚薬食品)と呼ばれる、直接的に性欲を高める食べ物や飲み物は存在しません。
精々、バナナやアワビなど性的な想像や感覚を呼び覚ますような食材によって、性欲を掻き立てることがあるかもしれない程度です。
ここで言う精力や性機能を高める食材とは、男性ホルモンの一種、テストステロンの生成や増強に効果がある、疲労回復に効果のある食べ物や飲み物のことです。
テストステロンは、男性の性機能(性欲や勃起力、生殖能力など)の維持に関係しているとても重要な男性ホルモンです。
性欲がなくなる、または衰えてしまう原因の一つに、男性の性機能を高めるために必要な栄養が不足していること挙げられます。
精力や性機能を高める食材やそれらに含まれる成分について詳しくご紹介します。
主に精力や性機能が高まる食材
※リンクをクリック、またはタップすると、ページ内の項目へ移動します
牡蠣

牡蠣に多く含まれる「亜鉛」は、性機能を高めるテストステロンの生成を促す働きがあるので、積極的に摂取したい栄養素の一つです。
また、牡蠣は「海のミルク」とも呼ばれることがあります。
その名の通り、牛乳と同じように、様々な栄養素がバランスよく豊富に含まれている食材なのです。
亜鉛のほかに「鉄分」や「ビタミンB12」「グリコーゲン」「タウリン」などを多く含んでいます。
鉄分やビタミンB12は、貧血や疲労回復に効果があります。
グリコーゲンは、肝臓や筋肉に蓄えられ、即効性のエネルギー源となるので、性行為において持続力を高めるのに役立ちます。
アミノ酸の一種であるタウリンは、血中のコレステロールや中性脂肪を減らし、ドロドロの血液を改善し、血流を良くする効果があります。
ビタミンB12は熱に弱いので、食べ方としては、生牡蠣で食べるのがおすすめです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 亜鉛 | 性機能向上作用 |
| 鉄分 | 貧血予防作用 |
| ビタミンB12 | 疲労回復作用 |
| グリコーゲン | 運動能力向上作用 |
| タウリン | 血流改善作用 |
ウナギ

夏バテの時期に多く食べられるウナギは栄養価が高く、「精がつく」食材で知られています。
ウナギには、牡蠣同様、「亜鉛」が豊富に含まれ、性機能向上に役立ちます。
ほかにも「ビタミンA」や「ビタミンB1」「ビタミンB2」などのビタミン群が免疫機能向上や疲労回復などに役立ち、性行為への意欲向上に効果が期待できます。
また、血流改善に役立つ「ビタミンE」や「DHA(ドコサヘキサエン酸)」「EPA(エイコサペンタエン酸)」なども豊富に含まれています。
定期的に食べておきたい食材ですが、割と高級な食材なので、日常の食生活に取り入れるのは、難しいかもしれません。
しかし、せめて土用の丑の日くらいは、蒲焼やうな重を食べておきたいものです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 亜鉛 | 性機能向上作用 |
| ビタミンA | 免疫機能向上作用 |
| ビタミンB1・B2 | 疲労回復作用 |
| ビタミンE | 抗酸化作用 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 中性脂肪低下作用 血小板凝集抑制作用 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) |
サーモン

サーモンに含まれるカロテノイドの一種である天然色素成分の「アスタキサンチン」は、強力な抗酸化作用や抗炎症作用を持っています。
この抗酸化作用は、トマトに含まれるリコピンの約2倍、ニンジンに含まれるβ-カロテンの約5倍、緑茶に含まれるカテキンの約560倍と言われています。
この強力な抗酸化作用によって、精子の劣化を防いだり、血管の老化を防いで血流を良くしたりする効果が期待できます。
また、抗炎症作用によって慢性的な炎症を抑え、筋肉の疲労を軽減する効果もあります。
その他、「ビタミンD」「ビタミンE」「DHA(ドコサヘキサエン酸)」「EPA(エイコサペンタエン酸)」などの精力アップに役立つ成分も豊富に含まれています。
ちなみに、サーモンの鮮やかなオレンジ色は、アスタキサンチンによるものです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| アスタキサンチン | 抗酸化作用 抗炎症作用 |
| ビタミンD | 免疫機能向上作用 |
| ビタミンE | 抗酸化作用 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 中性脂肪低下作用 血小板凝集抑制作用 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) |
アボカド

アボカドは、フルーツでありながら濃厚でクリーミーな味わいと脂肪が多く含まれることから、「森のバター」とも呼ばれています。
アボカドには、「カリウム」や「マグネシウム」「カルニチン」などが多く含まれています。
カリウムは、体内の余分な塩分の排出を促す作用があり、血圧を正常に保つ効果を持っています。
血の巡りを整え、健康的な体を作るという意味では、精力や性機能を高めることに繋がります。
マグネシウムは、体内で生成できないので、食事によって摂取しなければならない必須ミネラルの一つです。
マグネシウムには神経伝達を正常に働かせる作用があります。
脳から勃起神経を通して陰茎に勃起命令を行う上では重要な成分と言えます。
カルニチンは、体のほぼ全ての細胞内に存在しており、体内の脂肪代謝に欠かせない成分です。
脂肪を燃焼させ、エネルギーを産み出す働きがあるため、体脂肪の減少に効果があり、肥満防止に役立ちます。
また、カルニチンには男性ホルモンのテストステロンの働きを活性化させる効果もあり、性機能アップも期待できます。
アボカドは、一年中スーパーなどで安価に購入でき、半分にカットするだけでサッと食べられます。
なにかと忙しい方でも簡単に食生活に取り入れられるので、おすすめです。
余談ですが、アボカドは、「睾丸」という意味を持つメキシコのユト・アステカ民族が使うナワトル語「ahuacatl」が語源で、英語で書くと「Avocado」となります。
アボカドの形が睾丸に似ていることに由来しています。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| カリウム | 過剰塩分排出促進作用 |
| マグネシウム | 神経伝達制御作用 |
| カルニチン | 脂肪燃焼作用 |
肉類(牛肉、豚肉、羊肉など)

牛肉や豚肉、羊肉などの肉類には、「動物性タンパク質」が多く含まれており、効率的に摂取することが可能です。
動物性タンパク質を多く含む食べ物を摂取すると男性ホルモンのテストステロンが増加することが分かっています。
特に牛や豚の赤身肉には、豊富な動物性タンパク質だけでなく、亜鉛や鉄分などのミネラルも含まれており、テストステロン分泌を促進してくれます。
赤身肉は、脂肪が少なくヘルシーなので、おすすめです。
タンパク質は、男性的なたくましい体を作るのに欠かせない成分でもあり、勃起力にも関わるので、積極的に摂取していきましょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 動物性タンパク質 | 男性ホルモン活性化作用 |
マムシ

マムシは、古くから血行促進や滋養強壮、精力増強に効果があるとして漢方薬や栄養ドリンクなどに利用されています。
漢方の世界では、マムシの皮や内臓を取り除き、棒状に乾燥させたものを反鼻(ハンピ)や五八霜(ごはっそう)と呼びます。
マムシには、ペプチド(アミノ酸の集合体の総称)の「シスタチオニン」という成分が多く含まれています。
マムシの持つシスタチオニンの濃度は、牛肉の約80倍以上、ウナギの約2,000倍以上とも言われています。
シスタチオニンは、人の体内で分解されず、腸内でそのまま吸収され、「グルタチオン」という抗酸化物質に変換されます。
グルタチオンの抗酸化作用によって、血流改善が期待できます。
また、グルタチオンには、有害なミネラルを体外に排出するのを促すデトックス効果もあり、疲労回復に役立ちます。
疲労が回復することにより、低下していた性欲を間接的に回復することが期待できます。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| シスタチオニン(グルタチオン) | 抗酸化作用 解毒作用 |
スッポン

精力増強と言えば、スッポンも有名な食材ではないでしょうか。
スッポンもマムシ同様、古くから漢方薬や栄養ドリンクなどに利用されています。
良質な「動物性タンパク質」に加え、9種類の必須アミノ酸やミネラル、ビタミン、DHA、EPAなどが豊富に含まれています。
男性ホルモンを活性化させるだけでなく、疲労感の緩和に役立ちます。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| 動物性タンパク質 | 男性ホルモン活性化作用 |
オットセイ

絶倫動物として知られるオットセイには、「カロペプタイド」という成分が含まれており、精力や性機能を高めるのに役立ちます。
オットセイは、繁殖期に1頭のオスが20頭~30頭以上のメスを従えてハーレムを作り、飲まず食わず1ヵ月もの間、子作りに励むことができます。
ほかの動物には見られない、その繁殖力にはカロペプタイドが関係していることが分かっています。
カロペプタイドは、オットセイの筋肉から抽出される良質なタンパク質で、9種類の必須アミノ酸を含んでいます。
血管拡張作用によって血流を改善させ、さらに新陳代謝を促進させる効果が期待できます。
また、新陳代謝促進作用によって、細胞の働きを活発にし、性機能の衰えを防止できると考えられます。
ただし、オットセイは簡単に手に入る食材ではありません。
カロペプタイドを摂取する場合は、サプリメントや栄養ドリンクなどを活用すると良いでしょう。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| カロペプタイド | 血管拡張作用 新陳代謝促進作用 |
マカ

マカは、南米ペルーのアンデス山脈に自生する大根やカブと同じアブラナ科の植物の一種です。
栄養価が高く、古くから現地の人のスタミナ源として重宝されており、「アンデスの女王」とも呼ばれています。
マカは、天然のバイアグラと噂になるほど滋養強壮や精力増強に効果があるとされています。
その理由は、マカに含まれる「アルギニン」という成分が関係しています。
アルギニンは、血管拡張作用や抗動脈硬化作用、免疫機能向上作用などを持っています。
そのため、血管拡張による血流改善や免疫力向上による疲労回復などが期待でき、精力や性機能の向上に役立つのです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| アルギニン | 血管拡張作用 抗動脈硬化作用 免疫機能向上作用 |
高麗人参

高麗人参とは、別名オタネニンジンや朝鮮人参と呼ばれるウコギ科の多年草で、漢方薬や栄養ドリンクに利用されています。
人参という名前ですが、オレンジ色の野菜のニンジンとは全くの別物です。
高麗人参には、サポニン(サポゲニンと糖から構成される配糖体の総称)の「ジンセノサイド」という成分が含まれています。
ジンセノサイドは、中枢神経興奮作用を持っており、その影響で勃起機能の向上に役立つとされています。
中枢神経が活性化されることによって、脳への性的刺激情報の伝達を増幅させることが期待できるからです。
| 栄養成分 | 作用 |
|---|---|
| ジンセノサイド | 中枢神経興奮作用 |
EDを悪化させる可能性のある食べ物や飲み物
EDの予防や改善が期待できる食べ物や飲み物をご紹介しましたが、反対にEDを悪化させてしまう可能性のある食べ物や飲み物も日常生活には潜んでいます。
以下の食事には注意しましょう。
ED予防のために避けたい食事
※リンクをクリック、またはタップすると、ページ内の項目へ移動します
高カロリー食

高カロリー食は、EDの発症リスクを高める肥満や糖尿病などを招くので、食べるのを控えるか、食べ過ぎないようにしてください。
血中の中性脂肪やコレステロールが増加するので、動脈硬化や血行不良の原因にもなります。
成人男性が1日に必要な摂取カロリーは、2,500kcal前後と言われています。
高カロリー食は、1食分だけで1日の摂取カロリーの約半分を占める可能性があります。
高カロリー食を食べる場合は、その後の摂取カロリーに気を付けるか適度な運動を行いましょう。
代表的な高カロリー食(1食分のカロリー)
- カツカレー(約1,000kcal)
- カツ丼(約900kcal)
- ピザ(約850kcal)
- カルボナーラスパゲッティ(約750kcal)
上記の高カロリー食以外にも揚げ物や脂身の多い肉類、スナック菓子、カップ麺などもカロリーが高い傾向にあるので、注意しましょう。
高塩分食

高塩分食は、EDの発症リスクを高める高血圧や腎機能の低下などを招くので、食べるのを控えるか、食べ過ぎないようにしてください。
また、塩分を摂取しすぎると、血圧が上がりやすくなり動脈硬化の原因にもなります。
例えば、カップラーメンやインスタントラーメンをスープまで飲み干すと塩分を過剰に摂取する可能性が高くなります。
成人男性が1日に摂取しても良い塩分は、厚生労働省の基準で7.5g未満と言われています。
ただし、世界保健機関(WHO)の基準では、5g未満となっているので、なんにせよ減塩食に努めたほうがよさそうです。
代表的な高塩分食(100g中の塩分)
- イカの塩辛(約8g)
- カップラーメン(約6g)
- インスタントラーメン(約5g)
- いくら・すじこ(約2g~5g)
上記の高塩分食以外にも外食やコンビニ弁当、インスタント食品なども塩分が多い傾向にあるので、注意しましょう。
高脂肪食

高脂肪食は、EDの発症リスクを高める脂質異常症(高脂血症)などを招くので、食べるのを控えるか、食べ過ぎないようにしてください。
また、脂肪を摂取しすぎると前立腺がんの発症リスクも高めることになります。
前立腺がんは、EDと深く関係している病気の一つなので、脂肪を控えた食事が大切です。
成人男性が1日に摂取しても良い脂肪は、約50gと言われています。
ただし、脂肪を摂取する際は、炭水化物やタンパク質とともにバランスよく摂取することが大切です。
代表的な高脂肪食(100g中の脂質)
- クレープ(約20g)
- ハンバーガー(約14g)
- ミルフィーユ(約13g)
- フライドポテト(約11g)
上記の高脂肪食以外にも乳製品(生クリームやチーズ、バターなど)やマヨネーズ、ファーストフードなども脂肪が多い傾向にあるので、注意しましょう。
まとめ~食事の改善でEDを予防しよう~
乱れた食生活はEDの発症、悪化にも繋がります。
特に食事が高カロリー、高塩分、高脂肪の方はEDを悪化させてしまう恐れがあります。
今回紹介した血流を改善してくれる食材、精力や性機能が高まる食材などを摂取しましょう。
併せてED治療薬の服用で、EDのさらなる改善が期待できます。
当クリニックではED治療薬の処方を行っていますので、ED治療でお悩みのある方はお気軽にご相談くださいませ。


スタッフより

クリニックコラムをお読みいただきありがとうございます!
いかがでしたでしょうか、参考にはなったでしょうか?
いま、なんらかの症状でお悩みのそこのあなた!
一人で悩まず、まずはご相談ください。